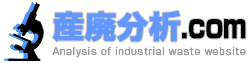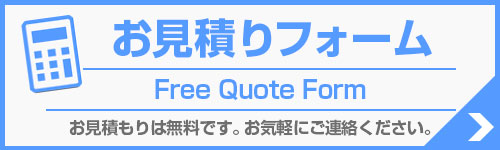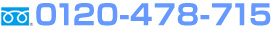【産廃分析】産業廃棄物とは? その3:産業廃棄物と一般廃棄物 ②

廃棄物とは?
前回に引き続き、今回も廃棄物について取り上げます。
前回「産業廃棄物とは? その2:産業廃棄物と一般廃棄物 ①」
前々回「産業廃棄物とは? その1:廃棄物と有価物」
一般廃棄物(一廃)
前回、廃棄物は大まかに産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分類している点を説明しました。産業廃棄物については前回の説明のように、複雑な決め事が多かったですが、一般廃棄物については、考え方は比較的シンプルで、「産業廃棄物(産廃)以外の廃棄物」を一般廃棄物(一廃)としています。
しかし、字面としてはシンプルなのですが、結局のところ産廃とは何なのかを理解していないと明確にならない定義のため、しっかりと区別するためには相応の知識・経験が必要となります。
一般廃棄物には以下の3種があります。
特別管理一般廃棄物(特管一廃)
一廃のうち、特定の有害物質を含む廃棄物群を指します。特管一廃で代表的なものは、家庭用家電のPCBを含む部品や、水銀を使用した製品などが挙げられます。特管物については後のコラムにて改めて取り上げますが、通常の廃棄物の処分方法が通用しない物質を含む・使用するものが対象となることが多いです。
事業系一般廃棄物(事業系一廃)
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、一般廃棄物として扱われるものを指します。詳しくは前回のコラムにて説明した通りとなります。
上記以外の一般廃棄物
特管一廃、事業系一廃どちらにも当てはまらない一廃は、その他の一廃(ただの一廃)として扱われます。事業系一廃に対して、家庭系一般廃棄物(家庭系一廃)と称されることもあります。
特管一廃と事業系一廃は非常に限定的なものなので、一廃というと家庭系一廃を指すことが多いです。大まかに一廃とは、「一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ類」と考えますと分かりやすいかもしれません。
産廃と一廃の違い
産廃と一廃の定義について説明してきました。大小様々違いはありますが、特に重要な違いについて触れておきたいと思います。それは廃棄物の処理の責任者についてです。
産廃は基本的に排出者自らに処理責任があります。自社にて発生した産廃については、自社に処理処分の責任があります。
また産廃の収集運搬や処理処分を行う者は、それぞれ専用の許可を得て行う必要があります。それらの許可を持っていない者が産廃を処理する場合、収集運搬や処理処分が可能な業者と自ら直接契約し、適正に処分することを求められます。もし契約した業者が不正を行った場合、処理責任のある排出者も同様に不正の責任を負うことになります。
産廃は都道府県境を超えた広域移動が認められていますので、発生した自治体外にて処分することも可能です。(ただし、発生・処分先の自治体とそれぞれ契約したり、移動の際は法令に定められた方法に則って適正に運搬する必要があったりと、簡単ではないことが多いです。)
一方で一廃は市町村区域内での処理を原則としており、基本的に市町村に処理責任があります。家庭ごみの収集を自治体で行っているのはこのためです。区域内での処理を原則としていますので、一部例外を除き、一廃は広域の移動は認められていません。したがって市町村ごとに保有する処理能力が異なる都合、市町村ごとに別個の処理処分のルールが決められています。
特に重要になるのは、産廃の処理責任が排出者にある点です。産廃は排出者が適正に処理処分する必要があるため、「産廃ではないと思って」不適切な方法で処分してしまうと、違法となる可能性があります。しかし、下記の2点の影響もあり、産廃か一廃かの判断が難しいケースも少なくありません。
・一廃として扱うものの範囲が、市町村ごとに異なる
・産廃の判断定義が自治体によって異なる
したがって前回も述べましたように、廃棄物の処理処分に関しては、管轄自治体の見解を踏まえた上で、産廃・一廃を適切に区別し、それぞれ適正な手順にて処分することが求められます。
なお前述しましたように、産廃の移動や処理処分を行うためには専用の許可が必要となります。「産廃を埋める」という行為は処分に該当しますので、たとえ自社の敷地内であっても、許可を得ず産廃を埋め立てる行為は違法となります。産廃の焼却なども同様ですので、適正な処理処分についてもよく知っておく必要があると思われます。
産業廃棄物に関するお問い合わせ・お見積依頼
ご相談・お問い合わせは下記からお気軽にご連絡ください。